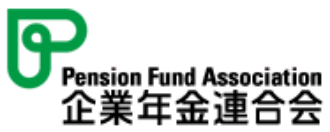よくあるご質問 FAQ
下記のよくあるご質問をご確認ください。
事業について
企業年金スチュワードシップ推進協議会とは、どのような組織ですか?
当協議会は、企業年金が協働して運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリング(協働モニタリング)するために設立された組織です(規約 第1条)。企業年金連合会の会員・非会員を問わず、全てのDB(確定給付企業年金(基金型・規約型)及び厚生年金基金)を対象としており、当協議会への入会による会費は無料、事務は企業年金連合会が行いますので、各企業年金では、コストや手間をかけずに、運用機関のスチュワードシップ活動のモニタリングを行うことができます。
スチュワードとは、執事、財産管理人を意味し、スチュワードシップは、財産を管理することを任された者の責務のことです。2014 年 2 月に、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」として「スチュワードシップ責任」を果たすにあたり有用と考えられる原則を定めた「日本版スチュワードシップ・コード」が策定され、企業年金を含む機関投資家に対して、コードを受け入れる旨を表明(公表)することが期待されています。
日本版スチュワードシップ・コードにおいて、「『スチュワードシップ責任』とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG 要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」(最終受益者を含む。以下同じ。)の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。」とされています。
また、企業年金などアセットオーナーに対しては、実効的なスチュワードシップ活動が行われるよう運用機関に促すこと、運用機関に対してスチュワードシップ活動に関して求める事項や原則を明確に示すこと、運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングすること、受益者に対して年に1度報告を行うこと、が求められています。
企業年金が、それぞれ個別に委託先運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングするのは非効率です。そこで、企業年金が協働して実施することで、各企業年金の負担軽減を図るとともに、運用機関によるスチュワードシップ活動の実質化も期待できるのではないかと考えます。具体的には、企業年金から国内株式の運用委託を受けている全ての運用機関を対象に、①アンケート形式の調査による共通項目の定点チェック、②運用機関ごとに説明会を開催し協議会会員が協働して運用機関との対話を行う合同説明会、③全社から 1 年間のスチュワードシップ活動の状況と自己評価についてまとめたサマリー・レポートの提供を受け、毎年更新します。専用ウェブサイトから、これらの情報の閲覧やダウンロードを行うことで、運用機関のスチュワードシップ活動について必要な情報の確認を行い、ステークホルダーへの報告も容易に行うことができます。(「協働モニタリング実施に係る基本的考え方」参照)
企業年金スチュワードシップ推進協議会に入会することで、日本版スチュワードシップ・コードを受入れたことになりますか?あるいは、日本版スチュワードシップ・コードを受入れる必要が無くなりますか?
当協議会として日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明を行います(規約 第9条)が、それをもって入会した個別の企業年金が、日本版スチュワードシップ・コードを受入れたことにはなりません。また、当協議会に入会したことをもって、日本版スチュワードシップ・コードを受入れる必要が無くなるわけでもありません。スチュワードシップ活動は、各企業年金が自らのスチュワードシップ責任を果たすために行うものであり、当協議会の活動は、あくまでも、本来、各企業年金が行うべき運用機関のスチュワードシップ活動のモニタリングを効率的に実施するために行う取組です。
企業年金スチュワードシップ推進協議会が行う協働モニタリングは、アセットオーナー・プリンシプル補充原則5-1の「協働モニタリング」に該当しますか?
当協議会が実施する協働モニタリングは、アセットオーナー・プリンシプル補充原則5-1における「協働モニタリング」に該当する取組です。
(「『アセットオーナー・プリンシプル』(案)に対する意見募集の結果について」項番 96 参照)
企業年金スチュワードシップ推進協議会に入会し、協働モニタリングを行うことをもって、アセットオーナー・プリンシプル原則5をコンプライできますか?
アセットオーナー・プリンシプル原則5は、「運用委託先の行動を通じてスチュワードシップ活動を実施する」ことを求めており、日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明や協働モニタリングを必須としているわけではありません。受入れ表明の検討や協働モニタリングも選択肢として考えられるとしているだけです。ただし、当協議会が実施する協働モニタリングは、アセットオーナー・プリンシプル補充原則5-1の協働モニタリングに該当しますので、当協議会に入会し、協働モニタリングを行うことは、原則5をコンプライしていることを補強することになると考えています。
<参考:アセットオーナー・プリンシプルに関する取組方針 原則5の記載例>
当基金(当社)は、受益者等のために運用目標の実現を図るに当たり、投資先企業の持続的成長に資するよう、運用委託先の行動を通じてスチュワードシップ活動を実施します。
その際、運用委託先のスチュワードシップ活動を促し、その活動を効率的かつ実効的にモニタリングするため、企業年金スチュワードシップ推進協議会に入会し、協働モニタリング(複数の企業年金と協働して運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングする取組)を行います。
当協議会に入会するメリットとしては、①運用機関のスチュワードシップ活動に関する情報を効率的に入手できること、②加入者等に対するスチュワードシップ活動の報告の負荷を軽減できること、③アセットオーナー・プリンシプル原則5をコンプライすることを補強できること、④母体企業のコーポレートガバナンス・コード原則2-6(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)において、企業年金スチュワードシップ推進協議会に入会し、協働モニタリングを行っている旨を記載することで内容を補強できること、⑤委託先以外の運用機関のスチュワードシップ活動の情報も入手でき比較が可能となること、⑥他の企業年金との意見交換や情報交換を通じてスチュワードシップ活動の好事例が得られること、⑦国内株式運用の委託を受けている全ての運用機関を対象に協働モニタリングを行うことで、我が国におけるスチュワードシップ活動の実質化が期待できること、などが考えられます。
企業年金スチュワードシップ推進協議会は、いつ日本版スチュワードシップ・コードを受入れるのですか?
2025年3月28日に金融庁に対して受入れ表明を行い、正会員の名称について公表を行います(規約第9条第1項)。その後、正会員の名称は定期的に更新します。
入会及び退会について
誰でも企業年金スチュワードシップ推進協議会に入会できるのですか?
全ての確定給付企業年金を実施する事業主(規約型DB)、企業年金基金(基金型DB)、及び厚生年金基金は、入会することができます(規約 第4条第1項)。企業年金連合会の会員であるかどうかを問いませんし、入会に当たって、企業年金連合会の会員になることを条件とはしていません。なお、企業年金連合会の会員が納付した会費が、当協議会の運営の財源として充てられることはありません。
はい、可能です。日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明をしている企業年金には、「協力会員」として入会いただけます(規約 第4条第3項)。すでに独自に運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングしていると思いますが、入会いただくと専用ウェブサイトから運用機関の情報を一元的に確認でき、また、受益者等への報告書を作成する際も活用いただけるものと考えています。モニタリングの効率化にお役立てください。また、これまでの経験を活かし、当協議会の取組をサポートしていただけると幸甚です。
当協議会への入会は、企業年金スチュワードシップ推進協議会のウェブサイトから手続きをお願いします。
複数事業主により規約型DBを実施している場合は、代表事業主が手続きを行ってください。なお、申込の際、「担当者連絡先」の登録は、企業年金担当者に限らせていただきますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。
はい、いつでも任意に退会することができます(規約 第8条第4項)。その際には、企業年金スチュワードシップ推進協議会事務局まで、退会する旨のメール(pfa-ss@pfa.or.jp)を送信してください。退会されると、専用ウェブサイト構築後に発行されるIDとパスワードが無効となり、専用ウェブサイトへのアクセスができなくなります。運用機関の情報を閲覧したりダウンロードしたりできなくなりますので、ご注意ください。
退会後、いつでも再び入会することができます。再度、入会手続きをお願いします。入会後、専用ウェブサイトのログインに使用するIDとパスワードは新規に払い出されます。また、正会員の場合、退会により公表している名称が削除され、入会した際に再び名称を公表しますが、公表が数ヶ月後になる場合が有ります。
個別に日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした場合、企業年金スチュワードシップ推進協議会から退会することになりますか?
当協議会に正会員として入会後、日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした場合でも、自動的に退会となることはありません。その場合、正会員から協力会員に変更させていただき、公表している正会員の名称から企業年金名を削除いたします。受入れ表明をした場合には、企業年金スチュワードシップ推進協議会事務局まで、その旨メール(pfa-ss@pfa.or.jp)で連絡をお願いします。また、連絡がない場合であっても、金融庁が公表している「スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリスト」に企業年金名が掲載された場合は、同様の手続きを行います。
運営について
企業年金スチュワードシップ推進協議会に入会することで会費などの費用負担はありますか?
当協議会の会費は無料です(規約第8条第2項)。ただし、合同説明会や意見交換会、勉強会等の参加にかかる交通費その他の費用は、各自で負担をお願いします(規約第8条第3項)。
企業年金スチュワードシップ推進協議会に入会することで事務的な負担はありますか?
企業年金連合会が事務局となり(規約 第6条第2項)、運用機関からの情報の依頼と受領、専用ウェブサイトの更新を行い、合同説明会の企画、設定、案内、進行などを行いますので、当協議会に入会したことにより新たに事務的な負担が生じることはありません。ただし、協働モニタリングの活用しだいでは事務的な負担がかかることがあります。例えば、合同説明会、意見交換会、勉強会への参加頻度が高ければ、それだけ時間や労力がかかりますし、専用ウェブサイトから委託先以外の運用機関についても確認し評価を行えば、社数が多くなるに従い負荷はかかります。
企業年金スチュワードシップ推進協議会の運営に参加することはできますか?
当協議会の運営は、基本的に企業年金連合会で行います。当協議会の事業に係る重要事項については、企業年金連合会理事会で決定、変更を行い(規約 第7条第1項)、それに従い、事務局として企業年金連合会が運営します(規約 第6条第2項)。ただし、規約第7条第3項において、「具体的な事業実施の内容について検討するため、構成員及び事務局からなる運営委員会を設置することができる。」と定めていますので、当協議会会員の意向に基づき運営委員会が設置され委員として参加されれば、具体的な事業実施内容についての検討に参加することができます。
協働モニタリングについて
協働モニタリングは、運用機関が投資対象としている全ての資産におけるスチュワードシップ活動が対象となるのですか?
協働モニタリングでは、全ての運用機関が対象となりますか?
グローバル株式など、委託している運用の一部に国内株式が含まれる場合も対象となりますか?
協働モニタリングの対象となる運用機関はどのように選定されるのですか?
当協議会から各協会を通じて、企業年金から国内株式の委託を受けている運用機関に対し協働モニタリングへの協力を依頼します。協働モニタリングに協力している運用機関については、専用ウェブサイトで社名を公表しますので、委託先の運用機関が入っていない場合は、企業年金スチュワードシップ推進協議会事務局にメール(pfa-ss@pfa.or.jp)で連絡してください。当協議会から先方に依頼します。
協働モニタリングはいつから開始されますか?
2025 年秋以降開始する予定です。現在、運用機関に対し情報の提供を依頼しており、10 月初旬を目途にアンケート調査結果とサマリー・レポートに関する情報を専用ウェブサイトの会員ページに登録し、閲覧およびダウンロードできるようにします。そのうえで、10 月から翌年 3 月までの間に合同説明会を開催したいと考えています。6 月開催の株主総会終了後、1 年間のスチュワードシップ活動をモニタリングの対象期間とし、その後、同様の年次サイクルで実施します。
合同説明会への参加方法を教えてください。
合同説明会の開催時期について教えてください。
毎年 9 月から翌年 3 月までの間に実施したいと考えています。1 週間から 2 週間の間に 1 社のペースで、年間 20 社前後を目標に実施したいと考えています。
日程の都合で合同説明会に参加できない場合、後日、説明会の内容を確認することはできますか?
合同説明会はオンラインでの配信も行いますので、その録画を専用ウェブサイトからいつでも視聴できるよう配信します。視聴期間は 1 年間を想定しています。
委託先の運用機関の合同説明会が開催されない年は、その運用機関のモニタリングは実施しなかったことになってしまうのですか?
合同説明会は年間 20 社程度を目標に行いますので、委託先の運用機関の合同説明会が行われない年もあり得ます。また、対象となる運用機関は 100 社を超えるものと思われ、順番に合同説明会を行えば 5~6 年に 1 回の頻度になります。契約件数に応じて頻度を工夫するなどの対応も必要と考えていますが、いずれにしても委託先の運用機関の合同説明会が開催されない年は生じ得ます。一方で、当協議会において、毎年、全ての運用機関を対象に、アンケート調査とサマリー・レポートの提供を求めますので、この内容を活用していただければ、委託先のモニタリングを毎年、実施することができます。もちろん、各企業年金が運用機関と直接行うミーティングの際に、スチュワードシップ活動についても確認し、モニタリングを行うことができます。
委託していない運用機関の情報の取得や合同説明会への参加もできますか?
はい、可能です。専用ウェブサイトの情報の閲覧とダウンロードおよび合同説明会への参加は、契約の有り無しに関係なく可能です。ただし、合同説明会の参加申込みが多い場合は、契約の有る会員を優先させていただく場合があります。
協働モニタリングの結果、各運用機関のスチュワードシップ活動について、企業年金スチュワードシップ推進協議会として評価を行うのですか?
各運用機関のスチュワードシップ活動について、当協議会として統一的な評価を行うことはしません。当協議会が実施する協働モニタリングは、運用機関のスチュワードシップ活動を効率的にモニタリングするためのプラットフォームを提供するものです。これを活用して、個々の企業年金が委託先の運用機関を評価してください。
その他
スチュワードシップ活動に関する情報を得ることはできますか?
他の企業年金のスチュワードシップ活動の取組を参考にしたいのですが?
当協議会では、会員同士の意見交換会を企画したいと考えています。他の企業年金の取組について、意見交換会の機会を活用ください。
日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明について相談や支援をお願いできますか?
投資家のスチュワードシップ活動について企業側が理解することも重要なので、母体企業の IR 担当など企業年金関係者以外の者も協働モニタリングに参加することはできますか?
企業年金スチュワードシップ推進協議会への入会を機に、企業年金連合会への会員加入も検討したいがどうすればよいか。
会員のご加入については、会員サービスセンター会員課(電話:03-5431-8712 E-mail:kaiin@pfa.or.jp)までお問合せください。企業年金連合会では、ご加入いただいた会員の皆様へ、企業年金に関する各種情報の提供、相談・助言、研修事業等の様々なサービス(https://www.pfa.or.jp/kanyu/goannai/index.html)を提供し、企業年金の運営をサポートしています。また、現在、会員加入前の1年間、会員サービスを年会費無料でお試しいただける「トライアル利用(https://www.pfa.or.jp/kanyu/trial/index.html)」のお申込みを受け付けています。是非、ご検討ください。
その他のご不明な点につきましては下記までご連絡ください。
|
企業年金連合会 企業年金スチュワードシップ推進協議会事務局 |
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階 E-mail:pfa-ss@pfa.or.jp |
|---|